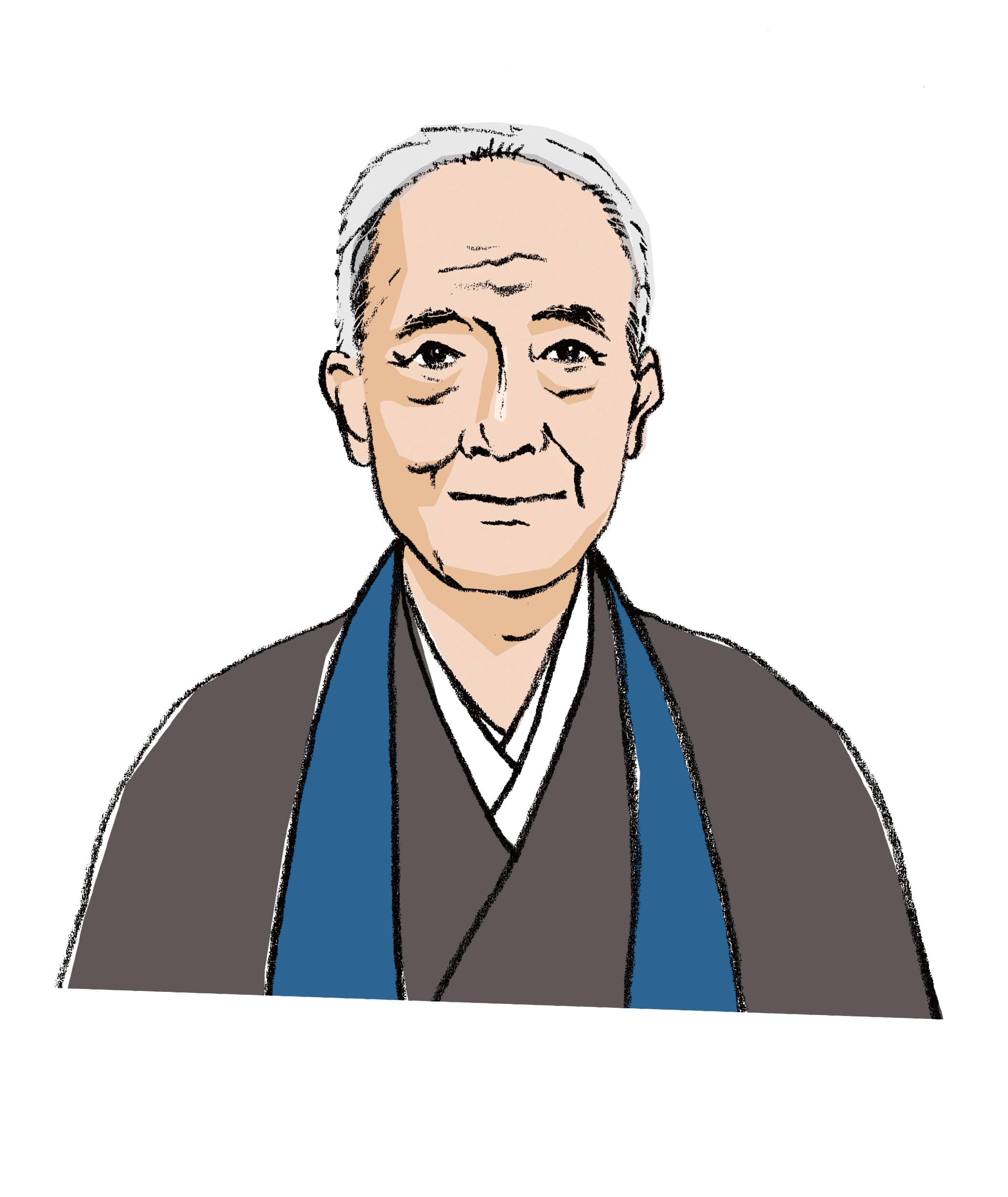本願ということについて、前回までにおおよそ説明をしてきましたので、今回からは、本願の課題をさらに展開してみたいと思います。本願には、その成就ということが教えられています。親鸞聖人は『教行信証』において、本願をいただくことについては、その成就の文を必ず参照されています。たとえば、第十八願を「信巻」で考察するに当たっては、第十八願に続いて第十八願成就文を引用されますし、第十一願を「証巻」で引用するに当たっては、その次に第十一願成就文を引用されています。
そして、本願の教えを聞法することも、その教えに遇うことができることも、実は本願の呼びかけによると見られるのです。本願には因果があり、本願が成就しようとする力、すなわち本願成就の力によって私たちに聞思の縁も与えられ、そこに参加することも可能になり、仏法との値遇も起こるのだと、受けとめられたのです。その果の力を「本願力」と言う、といただいたわけです。その本願力を、曇鸞大師は「他力」と言われたのです。それで、親鸞聖人は「行巻」の他力について明らかにする段で、「他力というは、如来の本願力なり」と言われているのです。
阿弥陀如来の本願は、名号として十方衆生に呼びかけ、阿弥陀如来の光明は十方世界を照らし続けているのだと言われます。しかし私たちは日常において、そのことには無関係だと思っています。それはこの光明も名号も、苦悩の娑婆(自我意識で感じる私たちを取り巻く世界)から、苦悩のない大涅槃界(迷いを突破した仏陀の智慧の世界)へと私たちを導き入れようとして、形なき法性が教えとして言葉になってきているものだからなのです。これを「形なき法性の方便法身の形」と考えることができるのです。それで親鸞聖人は、これらの教えの言葉について、繰り返して「不可称・不可説・不可思議」であると示されているのです。
私たちが普通には考えてもいないさまざまの言葉を、本願力の表現として示しているのは、仏陀の教えがその覚りを衆生に受け取ってもらうための手立て(方便)としているためなのです。仏陀の覚りそのものは、本来は言葉を超えた一如法性の体験内容なのですが、それを僧伽に入門した人たちが、直接体験しようとして苦悩を超えることや煩悩から解脱するために、いかに難行苦行を尽くしてみても不可能だと実感したのでしょう。本願を聞き当てたのは、仏弟子たちのこのような苦闘の歴史の結果であったのですね。